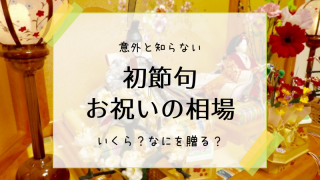女の子の初節句のお祝いは何をするのかわからないという人も多いでしょう。私にも12月生まれの女の子がいますが、何をしてよいものか色々と調べたものです。
お雛様を飾ったり、食事会を開いて、両親とお祝いをするという、大まかな雰囲気はわかっていても、いつ頃やるものなのかなども分からないですよね!
私の場合は3か月の時に初節句のお祝いをしましたが、首もすわっていませんでしたし、両親不在であり、今考えると次の年でも良かったな、とも思います。
早生まれの女の子にとっては、3月3日の初節句の時には、まだ新生児の状態ですね。無理のない範囲でご家庭の事情を考慮しましょうね💖
お祝の意味や、お祝いをするタイミングなど、きちんと知っておくと、安心して初節句を迎えることができますよ~一緒にみていきましょう
初節句の意味

初節句は赤ちゃんの成長をお祝いするだけでなく、これからも無事に成長するようにという願いや厄除けを行う行事です。
女の子は3月3日のひな祭り、男の子は5月5日のこどもの日に行いますが、これは季節の赤ちゃんにとって初めての季節の変わり目でもあります。
季節が変わっても、元気にすくすくと育つようにという願いが込められています。
お祝いには、ひな人形を飾って、今まで健やかに育ったことへの感謝と、これからの成長を願ってお参りをしたり、家族で食事を楽しんだりするのが一般的なお祝いの方法です。
初節句は何をするの?しなければならない?
初節句は、子どもの成長を願うための行事の一つです。
一般的には、ひな人形を飾って、お参りをしたり、食事会を開いて子供の成長をお祝いします。
しかし、絶対にしなくてはならないというものはないので、子どもの月齢や、それぞれの家庭の都合に合わせたスタイルで行うことが良いでしょう。
また、早生まれの子の場合、まだまだ小さな赤ちゃんです。
無理にお参りをしたり、お祝いをしなくても、翌年にしてもよいでしょう。
私の娘の初節句の時には、偶然にも両親ともに倒れ、翌年にと考えましたが、入院中の両親から『来年もどうなるかなんてわからないから、できる時にしてやってくれ』とお願いされました。
夫の両親は既に他界しているため、義祖母と私達家族で初節句を自宅で簡単に済ませました。
それぞれの事情に合わせた、無理のないお祝いをしてあげたいですね‼

初節句の主役は、子どもです。
子どもにとって負担になることや、ストレスになってしまうことは避けてあげましょう。
誰を招待すればいい?

初節句のお祝いは、多くの家庭で、両家の祖父母を招待して行います。
特に初めての子どもの場合には、盛大に行うことが多いです。
料亭や個室のあるレストランなどで部屋を借りて、両家の祖父母に両親と主役である子どもで行うことが一般的です。
そこに、兄弟や親せきなどを呼んで大勢でお祝いすることもあります。
地域によっては、自宅を開放して親戚を呼んで行う場合もあります。
必ず呼ばなくてはならないという決まりなどはありませんが、両家の両親が揃うことはあまりありません。
初節句など、節目のお祝いの際に両家の両親を招待することで、食事をする機会ができるので、家族の交流の場としてもよいでしょう。
食事会のマナーとあいさつの仕方

初節句を料亭などで行う場合には、まずは服装に注意しましょう。
初節句はお祝いの一つです。
家族で行うものであっても、カジュアルになりすぎない服装を心がけておきましょう。
↓↓↓初節句の時の両親・兄弟の服装の記事はこちら
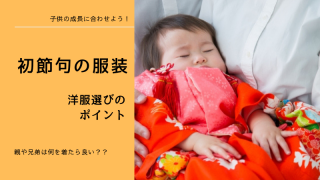
子どもにも、ベビードレスを着せたり、着物タイプのロンパースなどで少しおしゃれをさせてあげるのもよいでしょう。
かわいいベビードレスやおひな様のような十二単風の羽織などの記事はこちらから
↓↓↓

両親や親せきなど、ゲストを招待した場合には、きちんとご挨拶をしておきましょう。
食事が運ばれて来る前に、乾杯のタイミングなどで、子どもの父親がご挨拶をするのが一般的です。
子どものために集まってくれたことへの感謝の気持ちや、これからの成長を見守ってほしいということを、自分たちの言葉でしっかりと伝えましょう。
食事会など、楽しい時間を過ごしていても、赤ちゃんにとっては普段と違う環境で疲れてしまったりストレスを感じている場合もあります。
赤ちゃんの様子を見ながら、負担が掛からないように配慮して、短時間で楽しさが詰まった時間を過ごせるようにしましょう。
まとめ
初節句は、子どものためのお祝いです。
食事会など、楽しい時間を過ごしていても、赤ちゃんにとっては普段と違う環境で疲れてしまったりストレスを感じている場合もあります。
赤ちゃんの様子を見ながら、負担が掛からないように配慮して、短時間で楽しさが詰まった時間を過ごせるようにしましょう。
主役が子どもであることをしっかりと意識して、お祝いを行うタイミングや、場所などを工夫してあげることが大切です。
月齢に合わせて、早生まれの子は特に、負担にならないように翌年のひな祭りに行うことも検討しておきましょう。